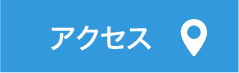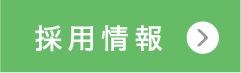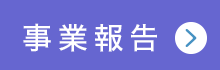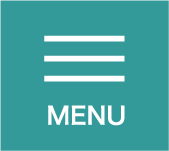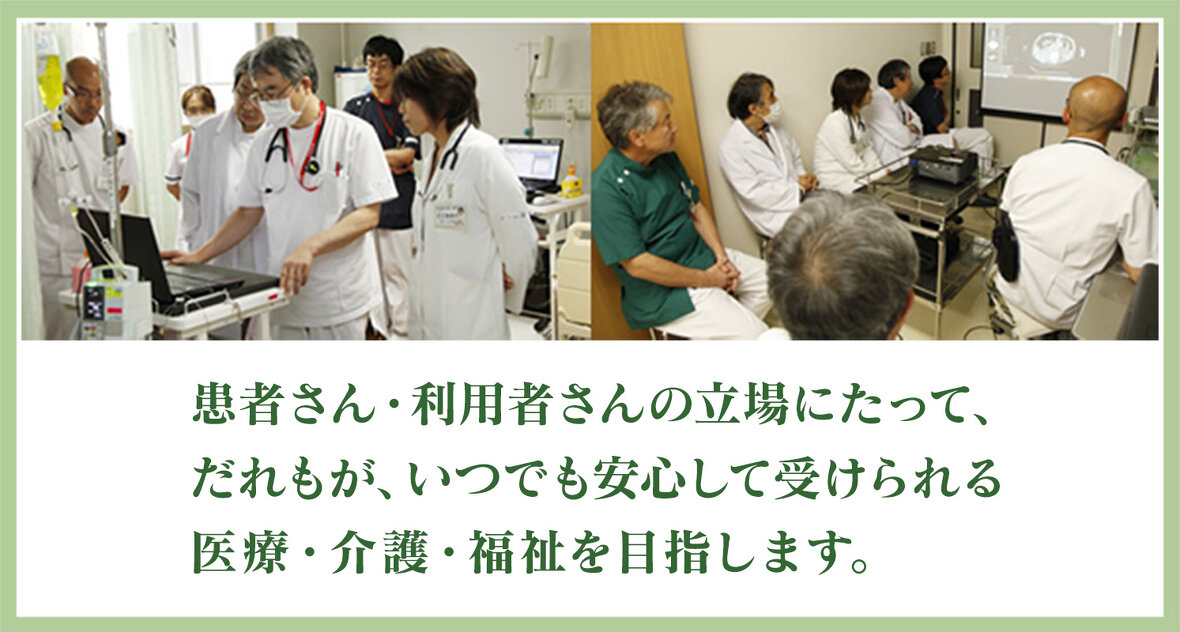理念・基本方針
諏訪共立病院 医療・福祉理念
基本方針
私たちの病院は、地域住民の「いつでも安心してかかれる自分たちの病院が欲しい」という思いからつくられました。私たちは、地域住民と共に、いのちと平和を守り、医療・介護・福祉を充実させていくために以下のことを宣言します。
一、私たちは、明るく誠実な対応に心がけ、患者さん、利用者さんの人権を尊重し、安全・安心・信頼・質の高い医療・介護・福祉を提供できるよう、常に学び、サービス向上に努めます。
一、医療と介護が連携を強め、「切れ目なく保障される無差別_平等の地域包括ケア」「誰もが安心して暮らせるまちづくり」に取り組みます。
一、差額ベッド料を一切いただかない姿勢を貫き、経営改善に努め、地域住民の共有の財産である病院を守ります。
一、生命を守る私たちは、戦争政策を絶対に許すことはできません。二度と戦争はしないと誓った日本国憲法第九条を守る運動を積極的に進め、戦争しない国の歴史を守り抜き、戦争法のすみやかな廃止を求めて、行動します。
諏訪共立病院
看護部理念
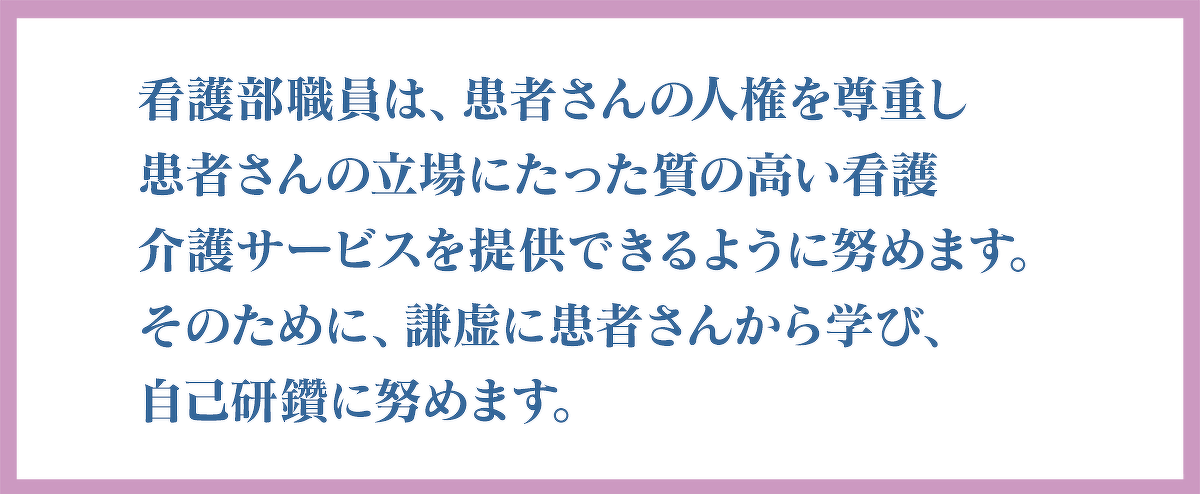
ハラスメントの防止メッセージ
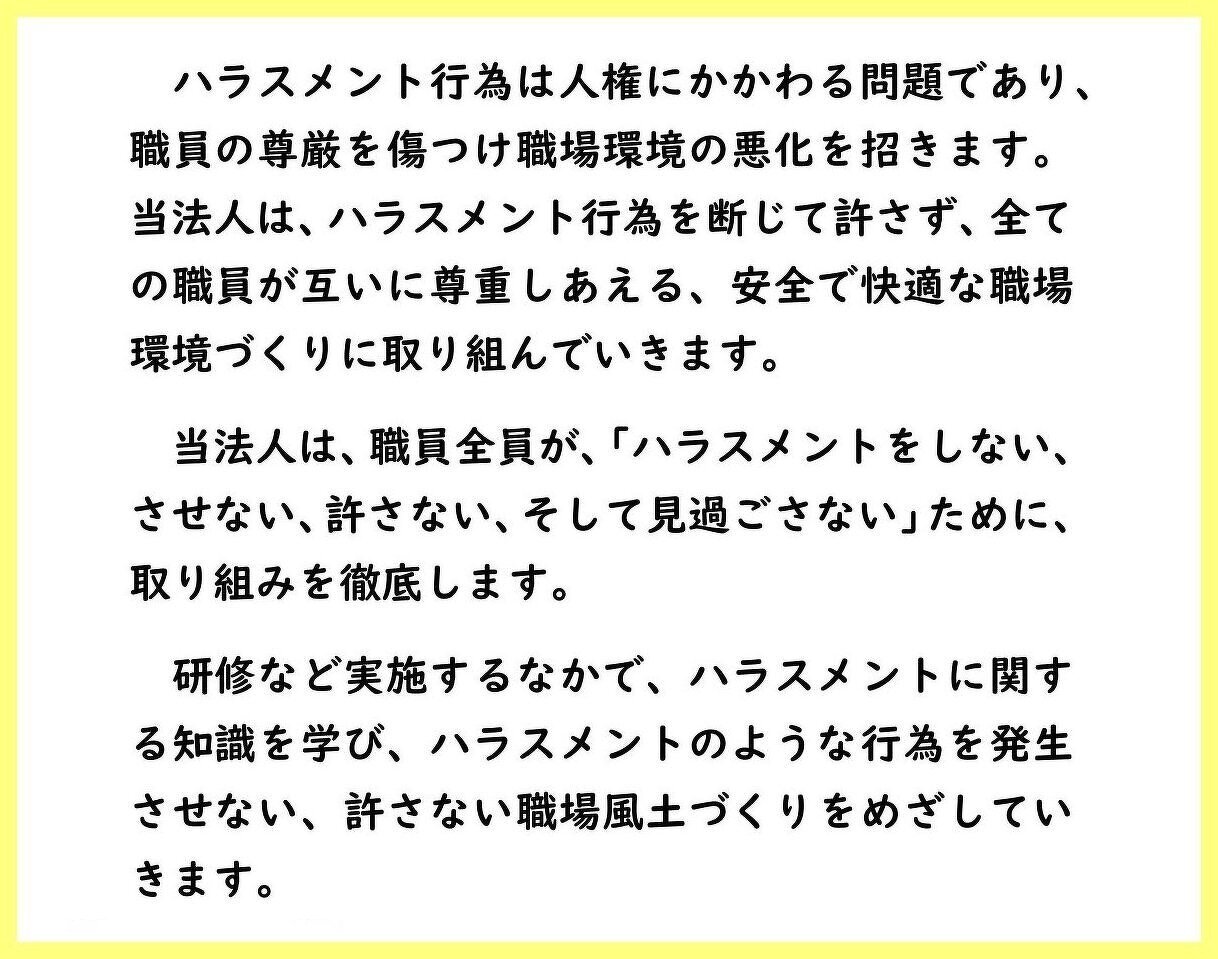
カスタマーハラスメントに対する基本方針
社会医療法人 南信勤労者医療協会
1 基本方針を公表する目的
南信勤労者医療協会(諏訪共立病院)は、だれもがいつでも安心して受けられる医療介護福祉を目指し、明るく誠実な対応に心がけ、患者さん、利用者さんの人権を尊重し、安全・安心・信頼・質の高い医療・介護・福祉を提供できるよう、サービス向上に努めています。これらの医療介護サービスを持続的に提供するためには、その医療介護を支える職員が、誇りを持って活躍し、尊厳が保たれていることが不可欠です。
日頃より当院をご利用いただく皆様からは、温かいご支援や貴重なご意見をはじめ、時には厳しいご批判を頂戴しており、日々ありがたく参考にさせていただいております。その一方で、ごくわずかではございますが、職員に対する誹謗中傷、自己中心的で理不尽な要求や悪質なクレームなどの迷惑行為事例が見受けられるようになりました。そのような行為から職員を守ることも持続的に医療介護を提供するためには不可欠と考え、「カスタマーハラスメントに対する基本方針」を公開いたしました。この取り組みを通じて、より良い医療介護を皆様に提供し続けるよう尽力して参ります。
2. カスタマーハラスメントに該当する行為
厚生労働省による「カスタマーハラスメント対策企業マニュアル」の記載を参考に、当院ではカスタマーハラスメントを、「患者利用者または家族による妥当性を欠いた要求や、社会通念上不相当な言動(威圧、暴言、暴行、脅迫等)により、当院職員の就業環境が害されること」と定義します。
例として次に挙げるような行為を当法人は拒否します。
- 来院者および職員に対するハラスメントや暴力行為、もしくはその恐れが強い場合
- 大声による罵倒、暴言または脅迫的な言動等により、他の利用者や職員に迷惑を及ぼすこと
- 解決しがたい要求を繰り返し、職員の業務に支障をきたすこと
- 建設設備などを故意に破損した場合
- 危険な物品を院内に持ち込んだ場合
- その他、一方的な主張等の長電話など医療介護に支障をきたす迷惑行為
「カスタマーハラスメント対策企業マニュアル」(厚生労働省作成pdf)
3. カスタマーハラスメントへの対応
病院や介護事業所において、上記のような暴言・暴力・迷惑行為があった場合、退去を命じます。応じていただけない場合は警察介入を依頼します。
当法人が悪質と判断した場合には、弁護士を含む第三者に相談のうえ、厳格に対処いたします。
また、上記のような行為は当事者と医療介護関係者との信頼関係を損ない,適切な医療介護の存続を困難にします。このような行為を繰り返す事で患者利用者さんとの信頼関係が破綻していると当法人が判断すれば、新たな診療・利用には応じられません。
予めご了承いただくとともに、ご理解とご協力をお願いいたします。
4. 職員への周知
当院では職員向けに以下を実施しております。
- カスタマーハラスメントに関する知識、対処方法について研修を実施します。
- カスタマーハラスメント発生時の対応体制を構築します。
- カスタマーハラスメント被害にあった職員のケアを最優先に努めます。
- より厳格に対応するために外部専門家(弁護士等)と連携します。
適切な意思決定支援に関する指針
1.基本方針
諏訪共立病院およびその関連施設で人生の最終段階を迎える患者が、その人らしい最期を迎えられるよう、厚生労働省「人生の最終段階における医療・ケアの決定プロセスに関するガイドライン」等の内容を踏まえ、多職種から構成される医療・ケアチームで、患者とその家族等に対し適切な説明と話し合いを行い、患者本人の意思決定を尊重し、医療・ケアを提供することに努める。
2.人生の最終段階における具体的な医療・ケアの方針決定支援
(1)本人の意思の確認ができる場合
- 方針の決定は、本人の状態に応じた専門的な医学的検討を経て、医師等の医療従事者から適切な情報の提供と説明がなされることが必要である。そのうえで、本人と医療・ケアチームとの合意形成に向けた十分な話し合いを踏まえた本人による意思決定を基本とし、多専門職種から構成される医療・ケアチームとして方針の決定を行う。
- 時間の経過、心身の状態の変化、医学的評価の変更等に応じて本人の意思が変化しうるものであることから、医療・ケアチームにより、適切な情報の提供と説明がなされ、本人が自らの意思をその都度示し、伝えることができるような支援が行われることが必要である。この際、本人が自らの意思を伝えられない状態になる可能性があることから、家族等も含めて話し合いが繰り返し行われることも必要である。
- このプロセスにおいて話し合った内容は、その都度、診療録に記録しておくものとする。
(2)本人の意思の確認ができない場合
次のような手順により、医療・ケアチームの中で慎重な判断を行う必要がある。
- 家族等が本人の意思を推定できる場合には、その推定意思を尊重し、本人にとっての最善の方針をとることを基本とする。
- 家族等が本人の意思を推定できない場合には、本人にとって何が最善であるかについて、本人に代わる者として家族等と十分に話し合い、本人にとっての最善の方針をとることを基本とする。時間の経過、心身の状態の変化、医学的評価の変更等に応じて、このプロセスを繰り返し行う。
- 家族等がいない場合及び家族等が判断を医療・ケアチームに委ねる場合には、本人にとっての最善の方針をとることを基本とする。
- このプロセスにおいて話し合った内容は、その都度、診療録に記載しておく。
(3)倫理委員会及び倫理コンサルテーション委員会での検討
上記(1)及び(2)の場合において、方針の決定に際し、以下のような状況がある場合は、倫理委員会及び倫理コンサルテーション委員会にて、医療・ケアチーム以外の者を加えて、方針等についての検討及び助言を行う。
- 心身の状態等により医療・ケアの内容の決定が困難な場合
- 本人と医療・ケアチームとの話し合いの中で、妥当で適切な医療・ケアの内容についての合意が得られない場合
- 家族等の中で意見がまとまらない場合
- 医療・ケアチームとの話し合いの中で、妥当で適切な医療・ケアの内容についての合意が得られない場合等
3.認知症等で自らが意思決定をすることが困難な患者の意思決定支援
障害者や認知症等で、自らが意思決定をすることが困難な場合は、厚生労働省の作成した「認知症の人の日常生活・社会生活のおける意思決定ガイドライン」を参考に、出来る限り患者本人の意思を尊重し反映した意思決定を、家族及び関係者、医療・ケアチームやソーシャルワーカー等が関与して支援する。
4.身寄りが無い患者の意思決定支援
身寄りが無い患者における医療・ケアの方針についての決定プロセスは、本人の判断能力の程度や入院費用等の資力の有無、信頼できる関係者の有無等により状況が異なるため、介護・福祉サービスや行政の関わり等を利用して、患者本人の意思を尊重しつつ厚生労働省の「身寄りがない人の入院及び医療に係る、意思決定が困難な人への支援に関するガイドライン」を参考に、その決定を支援する。
5.参考資料
- 人生の最終段階における医療・ケアの決定、プロセスにおけるガイドライン厚生労働省 2018年3月改訂
- 身寄りがない人の入院及び医療に係る、意思決定が困難な人への支援に関するガイドライン 研究代表差 山縣然太朗
- 認知症の人の日常生活・社会生活のおける意思決定ガイドライン 厚生労働省 2018年6月
諏訪共立病院